「善玉菌が増えて便通が良くなる」「免疫力がアップする」
多くの人がそんなイメージで、なんとなくヨーグルトを食べているのではないでしょうか。
私もです
毎日なんとなく健康に良さそうという理由で食べています
ヨーグルトと言ったらブルガリア
万博でもちろんブルガリアのパビリオンにも行きました
さて、1年くらいは継続して食べています
正直な所は目に見えた効果は分かりません
しかし、効果がありそうな事を毎日継続していると、プラセボも合わさって何かしらいい影響を与えると信じています
医学をやってると思うのは、プラセボは馬鹿にならないです
鰯の頭も信心から・・・
毎日100g程度のヨーグルトで、健康が得られるなら費用対効果は良いでしょう
デメリットも乳糖不耐症じゃない限りない
「体にいいらしい」だけで終わらせるのはもったいない話です。
医療者の建前、なんで健康に良いのかという質問には答える必要があるので
改めてしっかりと学ぶことにしました
ヨーグルトの健康効果は、腸内細菌と免疫系、そして胆汁酸代謝という複数の仕組みに裏づけられています
胆汁酸代謝は初めて聞きました
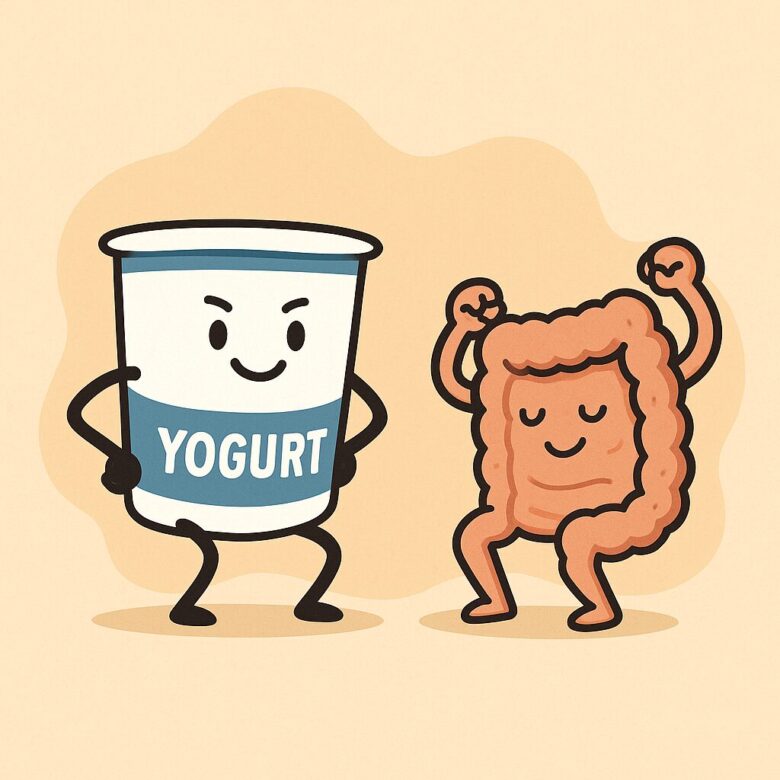
免疫力が“上がる”とはどういうことか
ヨーグルトに含まれる乳酸菌やビフィズス菌は、腸管関連リンパ組織(GALT)と呼ばれる免疫の最前線を刺激します。
ここではパイエル板などが「免疫の司令塔」として働き、次のような変化が起こります。
- IgA抗体の増加
粘膜表面で病原体をブロックするIgAが増えることで、ウイルスや細菌の侵入を防ぐ力が高まります。 - 自然免疫(NK細胞)の活性化
ナチュラルキラー(NK)細胞はウイルス感染細胞や初期がん細胞を直接攻撃する“第一の防衛隊”とでも言いましょうか
•臨床試験で確認された効果
実際の12週間ランダム化比較試験では、LcS発酵乳を飲んだ群は上気道感染(URTI)の発症率が22.4%にとどまり、対照群の53.2%より有意に低下しました。
風邪の発症率も18.4% vs 44.7%と半分以下に減少し、感染した場合でも症状日数は1.0日 vs 3.4日、1回の感染期間も2.8日 vs 5.0日と短縮されました。
さらに6週目には対照群で低下したNK細胞活性が維持され(P=0.013)、ストレスホルモンであるコルチゾールの上昇も抑えられました(P=0.045)。有害事象は報告されていません。
(Daily intake of fermented milk with Lactobacillus casei strain Shirota reduces the incidence and duration of upper respiratory tract infections in healthy middle-aged office workers)
これらの結果から、LcS発酵乳は免疫防御力を多方面から支え、風邪や上気道感染にかかりにくい体づくりを後押しすることが示されています。
今までは高齢者での研究がメインでしたが、中年にも効果あるのではとしっかりと検証した論文ですね
大切なのは免疫のバランスを整えること。
過剰な炎症を抑えながら感染防御を高める
これが「免疫力が上がる」の科学的な中身です。
短鎖脂肪酸がもたらす抗炎症作用
乳酸菌が食物繊維などを発酵すると、酢酸・酪酸などの短鎖脂肪酸(SCFA)が生まれます。
これらは腸だけでなく全身の炎症を和らげるカギを握っています。
Silva YP, Bernardi A, Frozza RL. “The Role of Short-Chain Fatty Acids From Gut Microbiota in Gut-Brain Communication.” Front Endocrinol. 2020;11:25. doi:10.3389/fendo.2020.00025の論文からは
腸内細菌が産生するSCFA(酢酸・プロピオン酸・酪酸など)は、腸‐脳軸を介して全身に作用し、免疫・神経・内分泌機能を調節する重要なシグナル分子であると報告しています。
主なポイントは以下の通りです。
- 免疫系:酪酸はヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)を阻害してTregの分化を促し、過剰な炎症を抑える。腸管バリアを守る作用も示され、炎症性腸疾患のリスク低下に寄与する可能性がある。
- 神経系:SCFAは血液脳関門を通過してタイトジャンクションを強化、ミクログリアの過剰活性化を抑え神経炎症を防ぐ。また神経栄養因子や神経伝達物質(セロトニン、ドーパミンなど)にも影響し、記憶・気分・エネルギー代謝を調節する。
- 疾患との関係:うつ病、自閉スペクトラム症、アルツハイマー病、多発性硬化症など多様な神経・精神疾患でSCFAの保護的役割が示唆されている。
このようにSCFAは腸内だけでなく全身、特に脳と免疫系をつなぐ重要なメッセンジャーとして、抗炎症や神経保護に関与しているとまとめています。
腸–脳軸(gut–brain axis)を介して免疫・神経・内分泌系に働きかける内容系の論文は一時期流行った思い出があります
胆汁酸代謝への影響と発がんリスク
胆汁酸は脂肪の消化に必須ですが、腸内細菌によって一次胆汁酸(コール酸など)が二次胆汁酸(デオキシコール酸=DCAなど)に変換されます。
この二次胆汁酸は大腸がんのリスク因子として知られています。
- Lidbeckら(1991, Curr Issues Intest Microbiol)は、大腸がん患者14名にLactobacillus acidophilus発酵乳(約3×10¹¹ CFU/日)を6週間摂取させ、
糞便中総胆汁酸が約15%減少、DCAが約18%低下したと報告しました。
乳酸菌は胆汁酸の脱水酸化(7α-脱水酸化)を行うClostridium属などの活動を抑え、DCAの生成を減らすと考えられています。
このDCA低下は、単なる腸内環境改善にとどまらず、長期的には発がんリスク低減に寄与する可能性があります。
胆汁酸に着目したこと全くなかったので、改めて勉強になりました
胆汁酸、特に二次胆汁酸には、いくつかのがん促進メカニズムが報告されています
| メカニズム | 内容 |
| 細胞障害・酸化ストレス | 胆汁酸は細胞膜やミトコンドリアを障害し、活性酸素種(ROS)や活性窒素種を発生させ、DNA障害・遺伝子変異を誘起 |
| シグナル経路活性化・過剰増殖 | EGFR/ERK、PKC、NF-κB などの経路が胆汁酸刺激で活性化され、上皮細胞の増殖や炎症性シグナルが促される |
| アポトーシス回避 | 慢性的な低濃度胆汁酸刺激は、アポトーシス抵抗性を獲得させ、異常細胞の排除が不完全になる |
| 核内受容体・シグナル制御異常 | FXR(Farnesoid X Receptor)、PXR、VDR などの胆汁酸応答核内受容体が胆汁酸の恒常性維持・解毒機能を担っていて、その制御異常は腫瘍形成を促す |
| 腸上皮バリア障害 / 炎症誘発 | 胆汁酸が腸上皮障害を引き起こし、バリア透過性増加、慢性炎症を誘起 → 炎症性サイトカイン、細胞傷害、発がん促進 |
胆汁酸の管理結構意味ありそうなんだよな
Bifidobacterium量と大腸がんリスク──長期コホート研究の示唆
最近の分子病理疫学研究では、長期的なヨーグルト摂取と大腸がん発症リスクの関係が、腫瘍組織内のビフィズス菌(Bifidobacterium)量によって異なることが報告されています
(Long-term yogurt intake and colorectal cancer incidence subclassified by Bifidobacterium abundance in tumor, 2023)。
米国のNurses’ Health StudyおよびHealth Professionals Follow-up Studyに参加した13万人以上、約300万人年の追跡で、腫瘍組織にBifidobacteriumが検出された症例では、
ヨーグルトを週2回以上食べる群は、月1回未満の群に比べて大腸がんリスクが約20%低い(HR 0.80, 95% CI 0.50–1.28)一方、Bifidobacterium陰性腫瘍ではそのような低下は認められませんでした。
特に近位結腸がんではこの差が顕著で、Bifidobacterium陽性腫瘍に限るとヨーグルト摂取がリスク低下に関連する傾向(HR 0.53, 95% CI 0.27–1.06)が示されています。
研究者らは、近位結腸は一次胆汁酸から二次胆汁酸への変換が盛んな部位であり、Bifidobacteriumは胆汁酸の脱抱合(bile salt hydrolase)活性を持つことから、
ヨーグルト摂取がBifidobacteriumを介して二次胆汁酸の生成抑制や腸管バリア強化をもたらし、それが腫瘍抑制に寄与している可能性を指摘しています。
やっぱり胆汁酸なんか・・・それが全て悪いわけではないと思うが、関係もありそう
結構おもろい論文やわ
良い胆汁酸にするには?
1. 食物繊維を十分に摂取
- 水溶性食物繊維(オート麦β-グルカン、果物のペクチン、海藻類など)は、腸内で短鎖脂肪酸(SCFA)を産生する発酵を促し、二次胆汁酸を作るClostridium属などの過剰増殖を抑えると報告されています。
- 不溶性繊維(野菜・全粒穀物)も胆汁酸を吸着して便中排泄を促進。
2. 発酵食品・プロバイオティクス
- ヨーグルト、納豆、味噌などに含まれる乳酸菌・ビフィズス菌は、胆汁酸脱抱合菌のバランスを改善し、二次胆汁酸の過剰生成を抑える可能性が示唆されています。
- 臨床試験ではLactobacillus acidophilus発酵乳が糞便中デオキシコール酸(DCA)を低下させた報告があります。
3. 高脂肪・高赤肉食を控える
- 飽和脂肪や動物性脂質の過剰摂取は胆汁酸分泌量を増やし、腸内での二次胆汁酸産生を助長。
- 加工肉・赤肉中心の食事は大腸がんリスクとも関連。
4. 規則正しい腸内環境の維持
- 十分な水分摂取・適度な運動で便通を良好に保つことが、胆汁酸が大腸内に長く滞留して二次胆汁酸へ変換される時間を短縮します。
5. 肝胆道疾患・肥満の管理
- 肝疾患・肥満・インスリン抵抗性は胆汁酸代謝異常の原因となります。
- 体重管理・適度な運動・糖質の質改善などで、胆汁酸プールのバランスが保たれやすくなります。
規則正しい食事は、脂肪とか糖尿病だけでなく、こういった胆汁酸にも良い影響を与えていそうですね
まとめ
ヨーグルトが健康に良い理由は、単なる「善玉菌が増える」では説明しきれません。
- 免疫系を整え、感染防御を高める
- 短鎖脂肪酸を介して慢性的な炎症を鎮める
- 二次胆汁酸(DCA)を減らし、発がんリスクを下げる
- Bifidobacteriumが多い腫瘍では大腸がんリスク低下がより顕著
これら複数の科学的メカニズムが、毎日ヨーグルトを食べ続ける価値をしっかり支えています。
「なんとなく体に良さそう」
その直感は、腸内細菌学と免疫学に裏づけられた確かな理由に基づいていると思われます
ということで毎日食べましょう
ちなみに明治ブルガリアヨーグルトは1970年の万博を機に1973年発売されたようです
ブルガリア館でも言ってました
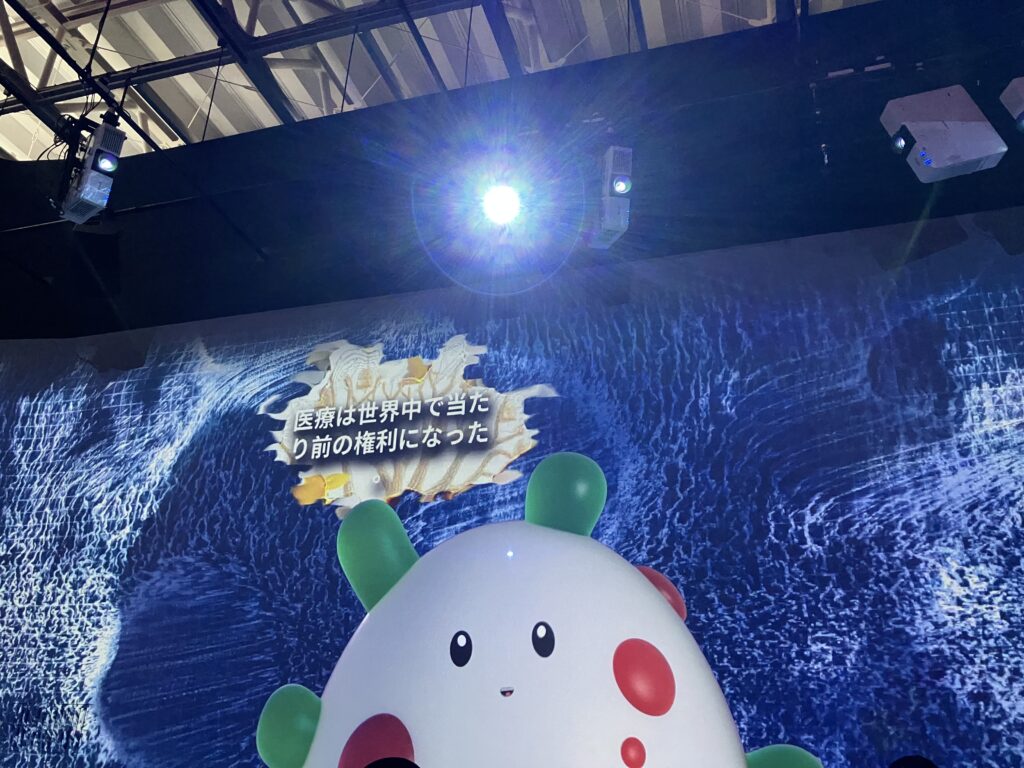
以上参考になれば幸いです




コメント