今回のタイトルは石丸桔平氏の人間親鸞です
Chat GPTに聞いても出てきません
浄土宗から浄土真宗までの流れは面白い
西欧にも宗教改革はあったが、浄土宗からの流れも日本の宗教改革みたいに思える
日本史の教科書で見てみますと、
法然上人が南無阿弥陀仏を唱える浄土宗を、そこから弟子の親鸞聖人が浄土真宗を開いたくらいしか書いていない
浄土宗までの南都の宗は、戒律に厳しくそもそも女人禁制
親鸞聖人の妻帯なんて、当時から禁忌中の禁忌であり日本の仏教史において革命
石丸桔平氏の人間親鸞の一説で
(ほんとうの道に生きようとして出家しながらいつの間にか道を踏み違えていた)
と言う箇所が非常に深くて良い
戒律を守って天台宗の中で出世していくことに疑問を感じるわけです
親鸞聖人はもとは天台宗であり、20年くらい修行している仏教エリートであることは重要
天台宗の教えを理解し修行した上での、妻帯すると言う決心
天台宗の厳しい戒律に疑問を感じ、さらに同僚が女性を追って比叡山を降りることから、悩みに悩み、人間とは何か、仏教とは何かを考え、比叡山を下り、法然上人と出会い行動していく
と言うのが大まかなストーリーです
そこまでの過程、その苦悩がまさに人間そのものであり、タイトル通り人間親鸞
読んでいる者自身にもその苦悩を感じさせる、名著と感じました
本を読む前に知ってても良い簡単な知識を以下に記載します
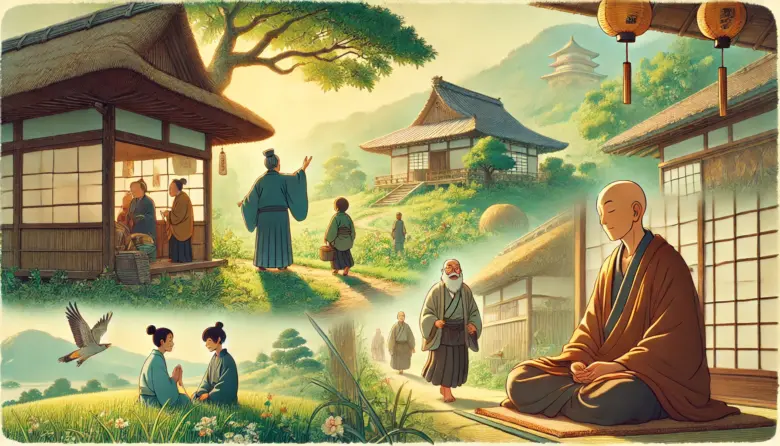
親鸞聖人について
Chat GPTより
鎌倉時代の僧侶であり、日本仏教に大きな影響を与えた浄土真宗の開祖です
1207年、念仏弾圧の嵐が吹き荒れる中、親鸞もまた流罪に処されます
「非僧非俗(僧でも俗人でもない)」と名乗り、妻帯し、庶民と共に生きる道を選びます
- 僧侶でありながら結婚し、家族を持った
- 身分に関係なく庶民と共に生き、信仰を広めた
- 罪人として扱われても、信念を貫いた
聖道門と浄土門
仏教の中には、大きく分けて 「聖道門」 と 「浄土門」 という二つの道があるとされます。
聖道門(しょうどうもん)とは、仏教の教えの中で、修行を積んで自力で悟りを得る道を指します。特に比叡山を中心とする天台宗や、禅宗などの伝統的な修行仏教の立場を表しています。
- 聖道門(しょうどうもん):自力修行によってこの世で悟りを得る道
- 浄土門(じょうどもん):阿弥陀仏の本願を信じ、念仏を称えて来世に浄土へ往生し、そこで悟りを開く道
聖道門の考え方
聖道門の代表的な仏教思想には以下のようなものがあります:
- 天台宗:比叡山を中心とし、一切衆生が仏性を持ち、自力修行によって悟りを得ることを目指す。
- 禅宗:坐禅や師との対話(公案)を通じて、悟りを得る。
- 華厳宗・法相宗:仏教哲学を深く学びながら、厳しい修行を通じて解脱を目指す。
法然上人とは?
- 平安時代末期から鎌倉時代初期の 浄土宗 の開祖
- 比叡山で天台宗の学問を修めるが、悟りを得ることの難しさを痛感し、「ただ念仏(南無阿弥陀仏)」を称えることで誰でも救われる という専修念仏の教えにたどり着く
- 1175年に浄土宗を開宗し、貴族から庶民まで幅広い層に浄土信仰を広めた。
法然上人の教え
- 専修念仏(せんじゅねんぶつ):「ただひたすら南無阿弥陀仏を称えれば、誰でも極楽浄土に往生できる」
- 選択本願(せんたくほんがん):阿弥陀仏は、すべての人を救うために「念仏を称える者を救う」と誓った。
- 自力を捨てて他力にすがる:「厳しい修行を積まなくても、阿弥陀仏の力(他力)によって往生できる」
法然上人と親鸞聖人の流罪について
法然上人の革新性
阿弥陀仏の「本願」に基づき、ただひたすらに「南無阿弥陀仏」と唱える(専修念仏)ことで、誰でも救われると説きました
既存の仏教(天台宗や密教など)と大きく異なる点です
修行せなあかんで、規律守らなあかんで、ていう既存仏教に対し、
念仏だけでええんですわ
そりゃ軋轢は生じる訳です
天台宗からの批判:天台宗の出身でしたが、その教えを「捨てて」念仏一行に帰したため、天台宗側からは激しく批判されました
興福寺の訴え(興福寺奏状):法然上人の弟子たちの布教活動によって、他宗派の教義が否定されたとする告発が起こり、朝廷に訴えが出されました
建永の法難(1207年):この訴えにより、法然上人とその弟子たちは処罰され、流罪にされました
法然上人は当時の仏教界に大きなインパクトを与える存在であり、結果として既存仏教との「対立構造」が生まれました
ある意味で革命、日本仏教の民主化とも言える動きです
貴族や有力者による仏教から民衆への仏教になったからですね
法然上人の専修念仏と、ルターの宗教改革との比較
違う点も多々あるのですが、西欧の宗教改革にもよく似ているように思います
共通点
1. 既存宗教への批判と民衆への信仰の開放
- 法然上人:難解な経典や修行が必要だった仏教に対して、「念仏一つで誰でも救われる」と説いた。
- ルター:カトリック教会の権威や贖宥状(免罪符)を批判し、「信仰と聖書のみによって救われる」と主張
→どちらも「宗教をエリートから民衆のものへ」と転換させた改革者と言えます
2. 経典の再解釈
- 法然:『無量寿経』など浄土三部経を重視し、「阿弥陀仏の本願」を中心に再解釈
- ルター:聖書を通して、「信仰義認(信仰によって義とされる)」を強調
→どちらも権威的な宗教組織ではなく、「聖なる言葉」に立ち返る姿勢をとった
3. 既存の宗教権威からの弾圧
- 法然上人:比叡山や興福寺から弾圧を受け、最終的には流罪に
- ルター:教皇から破門され、ヴォルムス帝国議会でも異端とされる
4. 後継者による発展
- 法然上人の弟子・親鸞聖人:さらに教義を徹底し、悪人正機説を打ち出す
- ルターの後継・カルヴァンなど:宗教改革をヨーロッパ全体に広げていく
「信仰は誰のものか?」という問いに対し、新しい答えを提示したという点では
法然上人とルターは東西の宗教界でとても似た存在と考えます
まとめ
人間親鸞は名著であり、めちゃくちゃおすすめです
親鸞聖人の決意のすごさを再度まとめておきます
- 「僧侶=独身」の常識を打ち破った
- それまでの仏教界では、僧侶が結婚することは「破戒」と見なされていました。
- 親鸞は、自分を「非僧非俗(僧侶でもなく、俗人でもない)」と位置づけ、従来の僧侶像を否定しました
- 「煩悩を捨てなくても救われる」という実践
- 従来の仏教では、煩悩(欲望)を捨てることが修行の目的でした。
- しかし親鸞は、「煩悩があっても、阿弥陀仏の本願によって救われる」と考え、自らの人生でそれを示した。
- 一般の民衆に寄り添う仏教へ
- 伝統的な仏教は貴族や僧侶中心でしたが、親鸞の浄土真宗は庶民のための仏教でした。
- 僧侶が結婚することで、僧侶と民衆の境界がなくなり、より身近な宗教となりました。
以上参考になれば幸いです


コメント