読書に夢中になっており、最近では明治以降から戦後初期の思想や歴史を調べております
子どもにもめちゃくちゃ本を読んでる親っていう印象を与えるので、それをみて本好きになってもらいたいものです
本ごとのつながり、連想ゲームのような形で、自分の中で点と点を結ぶように本を読んでいきたいと思っております
前回の丸山眞男氏関連として南原繁の戦後体制構想を読んでみました
/
東京大学総長くらいは、何かの本で知ってた気がします
思想的立場としては、南原氏の立場は、「戦後リベラル保守」あるいは「戦後左派の中の愛国派」といえるでしょう
とのchatGPTの答え
戦後の教育に携わったとも記憶しております
南原繁の戦後体制構想を読んで思ったことは、
内村鑑三と新渡戸稲造に影響を受けている
ご自身がキリスト教であるということ
教育基本法の制定の中心だったってことです
「日本はルネサンスを経験していない」という言葉も面白いなと思いました
ルネサンスの延長で宗教改革が起こり、キリスト教の権威が相対化されたという事実があり、天皇陛下の人間宣言を宗教改革と位置付けておられます
それも考え方の切り口は自分の中でなかったなと感じました
個人的な感想ですが、教育基本法ならびに教育に携わることで、日本国民の精神的にも日本神道からキリスト教的価値観への宗教革命を目指したのではないか、と考えてみました
GHQも日本へのキリスト教の布教に腐心したので、方向性は一緒だったのかも知れません
天皇を神格化する日本神道では無くなったかも知れませんが、神社参拝、お寺、葬式など神道や仏教の文化は根強いですし、何よりキリスト教徒は増えていない
現在の人口としては190万人程度で1%ですから、アメリカの占領下にもあったのにも関わらず(キリスト教のクリスマスは祝っていますが)、根本的には改宗していないというのは面白い結果と思います
インドもイギリスの長い統治下でしたが、イスラムとヒンドゥーからの改宗は少なそうですね
では、「戦後リベラル保守」あるいは「戦後左派の中の愛国派」って
左派なのか右派なのかよくわからないのでchat GPTに聞いてみます
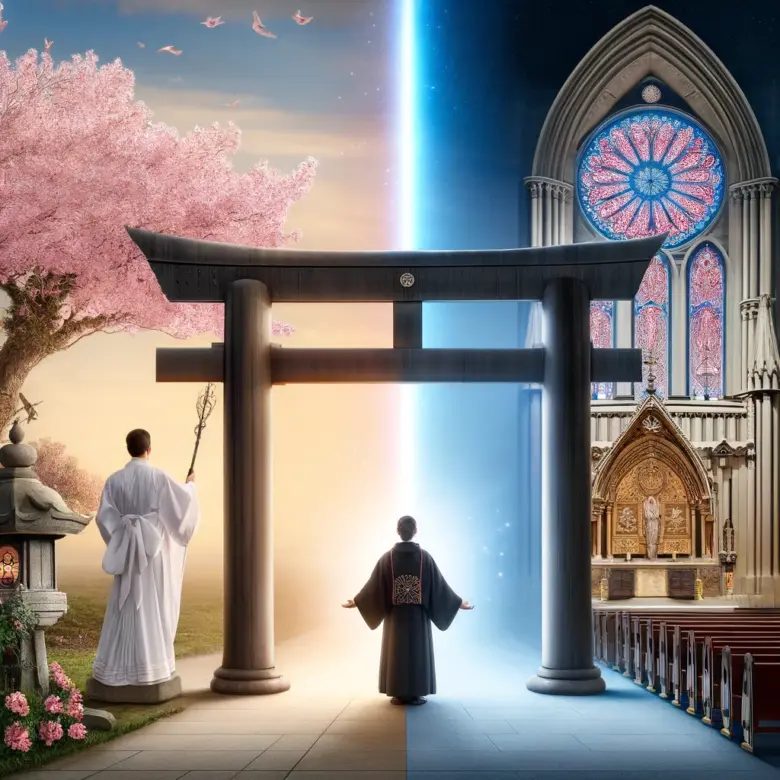
南原氏の政治的立場
(1) 左派的な要素
- 軍国主義・国家主義への批判
- 戦前の軍部独裁を厳しく批判し、民主主義の確立を主張。
- GHQの占領政策に一定の理解を示し、日本の戦後改革(憲法改正、教育改革)を支持。
- 社会正義と平等の重視
- 戦後の貧困格差是正を求め、社会政策の重要性を強調。
- 学問の自由を守る立場から、権力による思想統制に反対。
- 反戦・平和主義
- 日本が再び軍事国家になることを警戒し、憲法9条の理念を支持。
これらの点から、「左翼的」と見なされることもあります。
(2) 右翼・保守派的な要素
しかし、彼は単なる「左翼」ではなく、保守的な要素も持ち合わせていました。
- 皇室への尊敬
- 皇室を否定するような極端な左翼思想には与しなかった。
- 日本の伝統としての皇室の存在を重視し、象徴天皇制には一定の理解を示した。
- 愛国心
- 日本を独立した近代国家として発展させることを重要視し、単なる「反日的な左翼」ではなかった。
- 国家の誇りと道徳の重要性を説く姿勢は、左翼の中でも特異だった。
- 自主独立の精神
- GHQの占領政策に一定の理解を示したものの、日本が独立後は主体性を持つべきだと考えていた。
- 戦後の「占領体制」には批判的な面もあり、アメリカ一辺倒の政策には疑問を抱いていた
左派とか右派とかで表現できなさそうですね
戦後知識人?
ここら辺の言い方よくわかりません
大事なのは、熱心なプロテスタント系のキリスト教信者であるってことと思うんですよね
それが根底にあるのとないのでは、見え方が変わってくる
昭和研究会から教育刷新委員会への流れ
これも全然知らんかったんやけど、南原繁の戦後体制構想に記載されています。
昭和研究会は戦前の革新官僚や左派知識人の集まりで、教育刷新委員会は戦後の教育改革を担った組織ですが、連続性があったんですね
昭和研究会は、戦前の昭和初期に近衛文麿を中心として結成された政策研究グループです
ソ連のスパイである有名な尾崎秀実氏がいた組織ですね
昭和研究会も戦争に大きく関わっているので、これ単独の本も読みたいと思ってます
以下に教育刷新委員会の概要を記します
設立:1946年(GHQの指示により発足)
目的:戦前・戦中の軍国主義的な教育を一掃し、新しい民主主義教育を確立する
主な政策
- 教育勅語の廃止
- 1948年、教育勅語を公式に失効させ、軍国主義教育の根源を絶つ。
- 六・三・三・四制の導入
- 小学校6年+中学校3年+高校3年+大学4年のアメリカ型の学校制度を導入。
- 新しい教科書制度
- 戦前の国家主導の教科書(国定教科書)を廃止し、複数の教科書から選択できる制度へ変更
- 平和教育の推進
- 戦争の悲惨さや平和の大切さを教育するカリキュラムを導入
- 大学の自治の確立
- 戦前は国が大学の内容を統制していたが、戦後は大学の自主性を重視
旧制高校の廃止に関わったそうです
南原氏とキリスト教の関係
chatGPTにも聞いてみよう
① 宗教的背景
- 南原氏は、プロテスタントのクリスチャンであり、信仰を持つ知識人の一人でした。
- 特にカール・バルトの神学(バルト主義)に影響を受けていた。
- バルト主義は、ナチス・ドイツの全体主義を批判し、「人間の自由と神の絶対性」を強調する思想らしい
その考えからもドイツとの同盟は許されるものではなかったと想定されます
② キリスト教倫理と政治思想
- キリスト教的な「隣人愛」「平和主義」「社会的正義」の概念が色濃く見られる。
- 戦争や軍国主義を批判し、平和主義を唱えたことは、キリスト教の価値観に基づいていた。
③ 信仰と学問の融合
- 政治学者としての理論だけでなく、「倫理・道徳」の視点を重視した。
- キリスト教の価値観を基に、「民主主義は単なる制度ではなく、精神の問題である」と考えた。
③ 教育とキリスト教
- 東京大学総長として、戦後の教育の倫理的基盤としてキリスト教的価値観を取り入れるべきだと考えていた。
- 「教育刷新委員会」でも、戦前の国家主義的教育を否定し、人権・平和・道徳の教育を推進した。
まとめ
南原氏の戦後目指したことは、キリスト教をメインにした日本国民の精神的宗教改革というのが個人的感想です
教育勅語の廃止は、宗教改革がカトリック教会の権威を相対化したのと同じく、「国家による教育統制」を排除しようとする試みともいえ、
宗教改革では「個人の信仰の自由」が重視されていることを踏まえ、戦後日本において「個人の思考の自由」を重視し民主主義教育の推進をしております
東大総長で教育刷新委員会という情報と東大総長で教育刷新委員会でキリスト教信者という前提では、捉え方が変わると思いますので、本を読む、歴史を知るというのは大切と感じました
以上参考になれば幸いです


コメント