はじめに
日々の臨床では、西洋医学に基づいた治療を行っています。
しかし最近、漢方薬や自然療法に興味を持つようになりました。
実際、自分でも内服することがあります。
本記事では、そんな私が感じた**「漢方薬の可能性」、特に五苓散(ごれいさん)**の使用体験を中心に、東洋医学と西洋医学の違いや免疫へのアプローチを考察していきます。
よく知られた漢方薬たち|臨床でもよく使われる処方
| 漢方薬名 | 使われるシーン | 医師としての所感 |
|---|---|---|
| 葛根湯 | 風邪、乳腺炎 | 上半身に効きやすい印象あり |
| 抑肝散 | 夜泣き、せん妄 | 小児・高齢者で使いやすい |
| 六君子湯 | GERD、食欲不振 | 胃の動き改善に |
| 大建中湯 | 術後の腸管運動低下 | 外科術後に多用される印象 |
- 葛根湯:私自身は風邪の時に内服しますが、乳腺炎にも効果があると言われています。何でみたか忘れましたが、上半身に効きやすいはずです。上半身と下半身で薬効が違うなら機序がすごく知りたいです。
- 抑肝散:赤ちゃんの夜泣きからせんもうまで幅広い効用が期待できます。
- 六君子湯:胃食道逆流症への使用があり、漢方医以外でも使用するのではないでしょうか?
- 大建中湯: わりと腹部外科手術後に処方されているイメージです。
今あげた漢方薬は、多くの医師が知っているとは思います。
なぜ今、漢方に興味があるのか?
漢方は自然の植物・鉱物などから構成されており、副作用が少ない
カテキンや蜂蜜など自然由来成分が抗炎症作用や滋養強壮効果を持つ例も多い
健康意識の高まりから、食事・生活習慣と連動した医療として再評価したい
自分自身の食事内容を意識し健康に気をつけている影響だと思いますが、漢方薬というのは西洋医学の足りない所を補ってくれる可能性を感じました。
漢方薬に興味がある人は、どんなものか参考になると思います。
東洋医学と西洋医学の違いを整理

| 観点 | 西洋医学 | 東洋医学 |
|---|---|---|
| 主眼 | 発症後の治療 | 未病の予防 |
| 方法 | 検査・薬物治療 | 体質・バランス調整 |
| 対応 | 急性期に強い | 慢性症状や体質改善に強い |
西洋医学は「風邪を引いたら薬を出す」ですが、東洋医学では「風邪を引かない身体づくり」が基本。
そこに補中益気湯のような処方が関わってきます。
東洋医学のメリットは未病、すなわち病気になる前に対応する、ことと考えます。
もちろん急性期にも漢方薬は効果があるとも言われています。
西洋医学には予防的に未病に使用する薬はありません。
いわゆる滋養強壮に良い薬がないと思います。
例えば風邪をひいたら、対症療法しかありません。
風邪を引く前に飲む薬は特にありません。
サプリメントや栄養ドリンクくらいになるでしょうか。
風邪をひきにくくすると言ったら生活習慣の改善くらいしかないと思います。
免疫力をどう高めるか?|感染症の経験から感じること
風邪とはウイルス感染です。
ちなみにウイルスに抗菌薬は効きませんよ!!!
私は季節の変わり目に必ず風邪を引きます。笑
同じウイルスに暴露しても、症状が出る人・出ない人がいる…これは免疫力の違いだと思っています。
- 白血球、T細胞、B細胞、マクロファージ、NK細胞が働く
- サイトカイン(IL-6など)は炎症のカギを握る
- 適度な免疫応答=感染を防ぎ、強すぎるとサイトカインストーム
✨ 漢方薬は「免疫調整」や「抗炎症」作用があるとされるものも多い
- 例:補中益気湯、十全大補湯など
とはいえ、エビデンスが揃っているとは言えず、今後の研究が待たれます。
最近では、免疫力をUPさせることがよく話題になっていると思います。
免疫を上げる健康食品が多く紹介されていますが、本当に免疫力がアップするのか効果は正直わかりません。
しかし、今日は一つだけ私がお世話になっていた五苓散を紹介したいです。
散々免疫の話をしましたが、これは免疫とか全く関係ありません。笑
私が飲んだ漢方の中で一番効果を実感しました。
二日酔いの時に飲んでいた漢方薬です。
五苓散:私が最も効果を実感した漢方薬
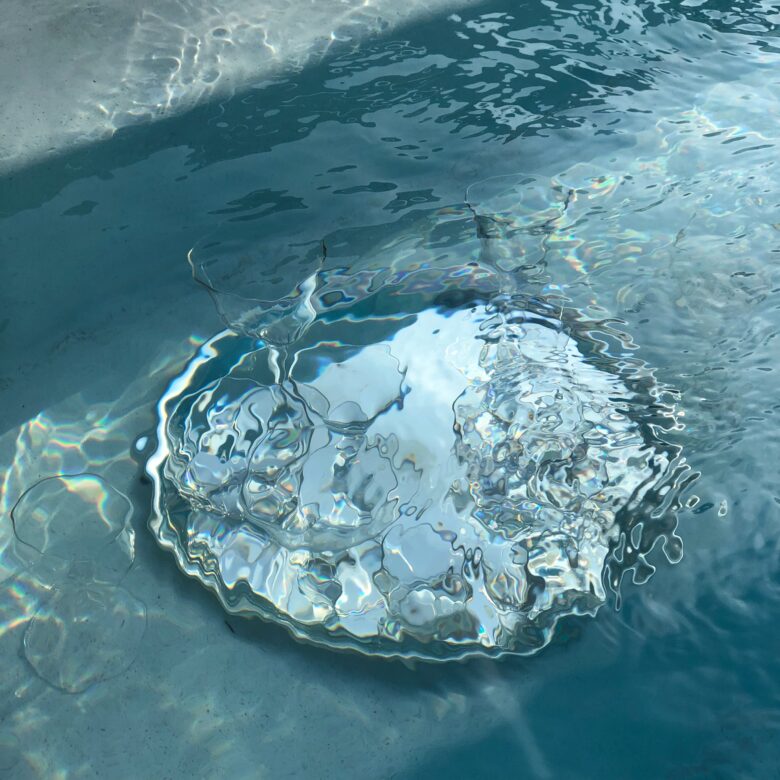
五苓散、僕の中で二日酔いにきく薬として認識しています。笑
用途:特に二日酔いで抜群の効果
- 口の渇き
- 尿量減少
- 胃腸の不快感
- むくみ、急性胃腸炎
成分と作用
| 生薬 | 主な作用 |
|---|---|
| 沢瀉(タクシャ) | 利尿、下痢改善 |
| 猪苓(チョレイ) | 解熱、利尿 |
| 蒼朮(ソウジュツ) | 整腸、利尿 |
| 茯苓(ブクリョウ) | 免疫調整、精神安定 |
| 桂皮(ケイヒ) | 抗炎症、血流改善(シナモン成分) |
重複している効果:利尿作用と胃腸保護
効用としては、口の渇きや尿量の減少がある人の症状を改善する。
水分代謝がうまくいかないことによる症状を改善させます。
具体的な症状は、浮腫、急性胃腸炎、二日酔いなどです。
上記にもありますが、生薬に抗炎症や抗酸化の効果があるというのが面白いですね。
科学的メカニズム|アクアポリンとの関係
科学的には、五苓散はアクアポリンという水チャネルの分子に作用することが報告されています。
アクアポリン2の発現を抑えるのはサムスカというお薬ですが、これはアクアポリン4を阻害します。
- 脳に多く存在するアクアポリン4の過剰な働きを調整
- 結果、脳浮腫の軽減・頭痛の緩和が期待される
西洋医学的に例えるなら:
サムスカ(トルバプタン)+ ガスター(胃薬)+ パントール(整腸剤)?
※あくまで私的な印象です。笑
まとめ:西洋医学+漢方という選択肢
東洋医学と西洋医学の簡単な違いを説明しました。
- 洋薬にはない**「滋養強壮」「免疫バランス調整」**を漢方は担えるかもしれない
- 私自身、五苓散は特に実感のある処方
- 今後は「予防医療」や「自然療法」との接点として漢方に注目していきたい
以上参考になれば幸いです
下記リンクは風邪の予防についての運動について考えているので興味があれば一読ください



コメント