はじめに
Xを眺めているとタメになるポストに出会うことが多い。
玉石混交感はあるが、医学系の投稿は論文紹介や症例報告もあり、日々目を通している
先日も「脱水と認知機能に関する論文」を紹介している投稿を見かけ、
「たかが水分不足が頭の働きに影響するのか?」と興味をひかれました。
実際に論文を探して読んでみると、わずかな水分減少でも脳に負担がかかることを示す2つの研究に出会いました。
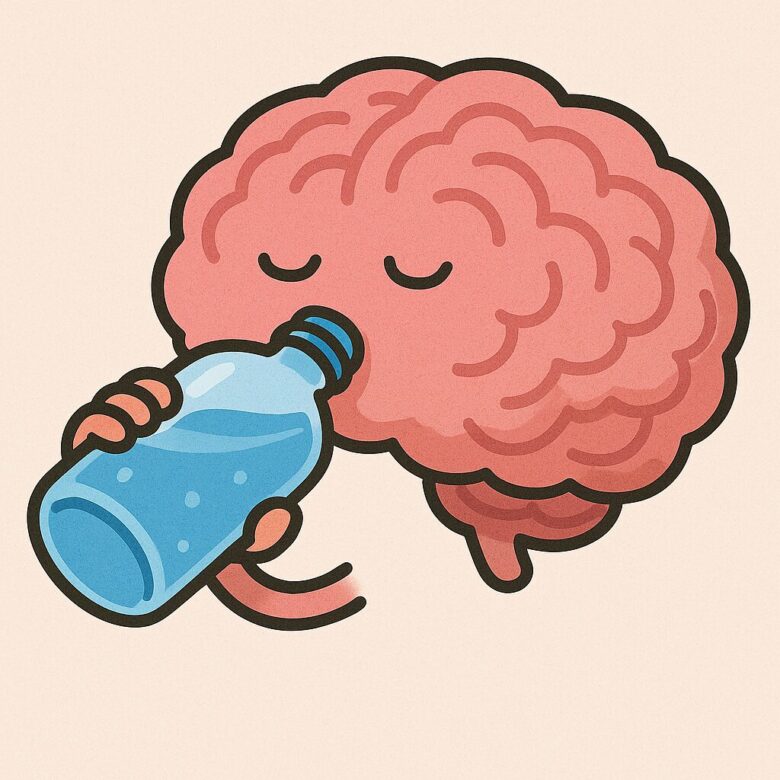
メタ解析:2%以上の脱水で認知機能が有意に低下
Wittbrodt MT, Millard-Stafford M. Dehydration Impairs Cognitive Performance: A Meta-analysis. Med Sci Sports Exerc. 2018;50(11):2360–2368. doi:10.1249/MSS.0000000000001682
研究概要
- 33件・413人の研究データを統合したメタ解析。
- 運動や熱ストレスを含むさまざまな状況での脱水と認知機能の関係を検証。
主な結果
- 体重2%以上の脱水で、全体的な認知機能が小さいが有意に低下(Hedges g = -0.21)。
- 特に注意力 (g = -0.52)、実行機能 (g = -0.24)、運動協調性 (g = -0.40) が影響を受けやすい。
- 熱環境や被験者の体力レベルによる差は大きくなく、脱水そのものが認知機能低下の主要因であることが示された。
結論
体重の約2%を失う程度の脱水は、注意力や判断力を落とす十分なリスクとなる。
2%ってめちゃくちゃ多くはないと思ってしまうが・・・
実験研究:体重0.8%減でも「脳震とう様」症状
Strüven A, et al. Impact of Preparticipation Hypohydration on Cognitive Performance and Concussion-like Symptoms in Recreational Athletes. Nutrients. 2023;15:4420. doi:10.3390/nu15204420
研究概要
- 健康なレクリエーションアスリート50名(18–50歳)が対象。
- 12時間の飲水制限で軽度脱水(体水分約2%減、体重0.8%減)を作り出し、
自転車運動後にSCAT3(スポーツ脳震とう評価ツール)で認知機能を評価。
主な結果
- 脳震とう様症状の総数が1.8→0.4件に増加、重症度スコアも4.4→1.0と有意に悪化(p<0.01)。
- バランス検査(タンデムスタンス)で誤りが増加(1.1→0.6回、p=0.02)。
- 記憶力・集中力には大きな差はなく、即時記憶のみわずかに改善。
- 電解質や血清浸透圧には変化なし。
結論
体重0.8%減というわずかな軽度脱水でも、脳震とうに似た自覚症状とバランス障害が出る。
スポーツ現場では脱水が脳震とう診断を混乱させる可能性があり、水分補給の重要性が改めて示された。
なぜわずかな脱水でも脳はストレスを受けるのか
数字だけ見ると「体重0.8%減なんて誤差では?」と思うかもしれません。
しかし脳にとっては十分なストレスになるようです
- 血漿浸透圧の上昇:神経細胞の水分バランスが崩れ、シナプス活動が乱れる。
- 脳血流の変化:体液減少で脳への血流が一時的に低下し、高次機能が鈍る。
- ホルモン応答:脱水でストレスホルモンが増加し、頭痛や倦怠感など脳震とう様症状を誘発。
体重で見ればわずかでも、脳の内部環境は大きく揺さぶられる。
もうちょっと詳しく考えると
1. 血漿浸透圧の上昇
体液が不足すると、血中のナトリウム濃度などの浸透圧が上昇。
主に運動での汗による水分喪失の場合はほぼ髙Na血症なはず
その後真水めっちゃのめば低Naになるかもだが
脳細胞は細胞外液より浸透圧が低いため、水が細胞内から外へ引き出され、細胞内脱水。
ニューロンの収縮は細胞膜のイオンチャネル配置や膜電位に影響を与え、シナプス前終末での神経伝達物質放出やシナプス後受容体応答が不安定になります。
その結果、注意力や記憶など高次認知機能が低下。
2. 脳血流の変化
脱水により循環血漿量が減少すると、心拍出量が下がり脳灌流圧も一時的に低下します。脳は自己調節機構によって一定の血流を保とうとしますが、体液減少が急激または重度の場合、この補償が追いつかず、皮質や海馬など高次機能を担う領域の酸素・ブドウ糖供給が一過的に不足。
これにより、思考の鈍化、集中力低下、頭痛などが起こります。
3. ホルモン応答
脱水は軽度のストレス反応として副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)やコルチゾール分泌も増加させ、交感神経活動が亢進。
これにより血管収縮・血圧上昇が起こり、脳の一部で一過性の虚血様変化が生じ、脳震とうに似た頭痛・めまい・倦怠感などが出現することがあります。
脱水はストレスであるって、大事な概念と思った
暑い環境では誰でも起こり得る:夏の万博を思い出す
気温が高く、人が多く、長時間歩き回る、そんな環境では軽度の脱水はあっという間に起こります。
水分補給を怠ると、集中力の低下や頭がぼんやりするなど、認知機能が落ちるリスクが確かに高まります。
私は真夏の万博を訪れましたが、とにかく暑く、人混みの中を長時間歩き続ける状況。
気がつけば「もしかして少し頭が働いていないかも」と思うほどでした。
実際、夏場は毎回2リットルほど水分を摂取していました。
2%に近いかも・・・・
私の総体重の2%に相当する水分量は秘密でありますが、それくらい飲まないと口渇が治らなかったです
上述しましたが2%程度の体重減少でも集中力や判断力が下がることが報告されています
当日予約がうまく取れなかったのも、脱水による集中力の低下のせいか・・・www
勉強するなら脱水じゃない方がいい?
そりゃそうな気がするが、chatGPTにも出力して細かく言語化してもらうか
脱水が学習・集中力に与える影響
- 認知機能の低下
体重のわずか 1–2%の水分喪失でも、注意力・短期記憶・反応速度の低下が複数の研究で示されています。 - 疲労感と頭痛
脳血流の一時的低下やホルモン応答により、軽い頭痛や倦怠感が起こりやすく、学習効率を下げます。 - 気分の変化
脱水はイライラ感や不安感を強めることもあり、集中の持続を妨げます
学習中の水分補給の目安
- 室内でも1時間あたりコップ半分〜1杯(100–200mL)程度を目安にこまめに飲む。
- 長時間続ける場合や暑い環境では経口補水液や軽く塩分を含む飲料が望ましい。
- のどの渇きを感じる前から少しずつ補給するのがポイント。
まとめ
- 2%を超える脱水では認知機能低下が顕著で、注意力・実行機能・運動協調性が影響を受ける。
- 0.8%程度の軽度脱水でも脳にストレスがかかり、脳震とう様症状やバランス障害を引き起こすことがある。
- 季節や環境に関わらず、喉が渇く前からこまめに水分補給する習慣が、脳のパフォーマンスを守る最もシンプルで確実な対策です。
ここで示した論文以外にもそれなりに脱水と認知のテーマは調べられているようです
では、脱水補正して万博に向かいましょう
以上参考になれば幸いです
参考文献
- Wittbrodt MT, Millard-Stafford M. Dehydration Impairs Cognitive Performance: A Meta-analysis. Med Sci Sports Exerc. 2018;50(11):2360–2368. doi:10.1249/MSS.0000000000001682
dehydration_impairs_cognitive_p…
- Strüven A, et al. Impact of Preparticipation Hypohydration on Cognitive Performance and Concussion-like Symptoms in Recreational Athletes. Nutrients. 2023;15:4420. doi:10.3390/nu15204420
nutrients-15-04420


コメント