非常に面白い
しかし500ページ以上でめっちゃ長い
やっと読めました
上も記事にしています
上巻では主に欧米諸国のインテリジェンス活動に焦点が当てられていましたが、下巻は一転して、日本の情報戦の実態に深く切り込んでいく構成になっており、読後の印象はまったく異なります
そもそも、学校の教科書って、どうしても「日本は侵略した」「負けた」「反省しよう」みたいなストーリーで終わりがちと感じます
もちろん反省は大事です、それだけでは歴史の立体感が伝わらない
実際には、その「負けるまで」「どう終わらせるか」に命をかけた人たちがいて、彼らの動きが戦争を終結させる決定的な力になったという側面は、教科書ではほとんど触れられていない。
春日井邦夫氏の『情報と謀略 下』が貴重なのは、その「見えない努力」に光を当てているところです
敗戦は確かに現実だったけれど、そこに至るまでに「いかに被害を最小限にしようとしたか」「終戦への糸口をどう探ったか」という情報戦・交渉戦があったことは大事な視点です
下、で個人的には面白かったのは
「昭和の天才」と称された仲小路彰氏に焦点を当てている
サイパン上陸以降からの終戦へと向けた陸軍、海軍の関係
終戦後の事件について、です
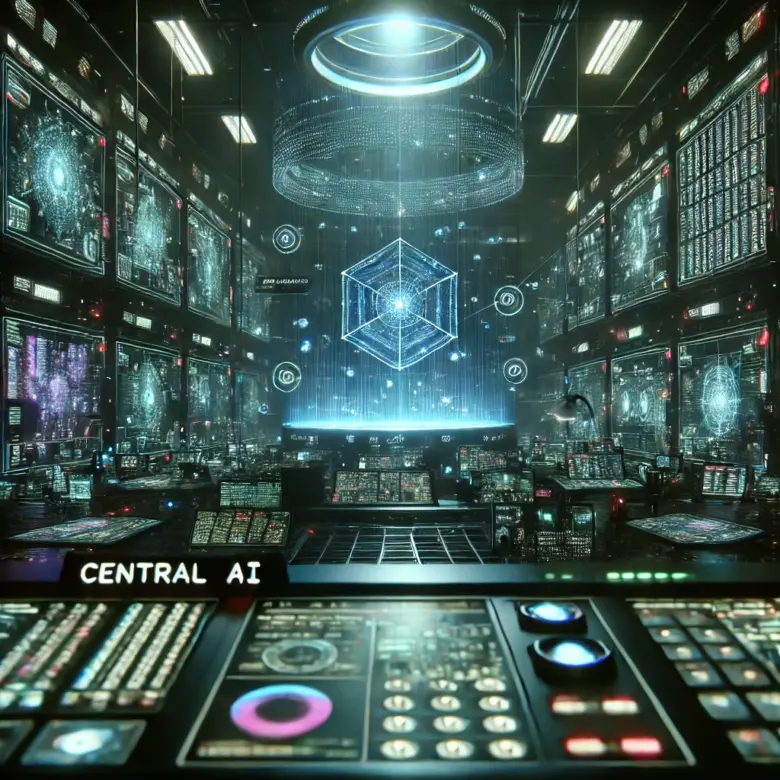
仲小路彰とは?
全然知らんがな
chatGPTに聞いてます
仲小路 彰(なかしょうじ あきら、1901年2月26日 – 1984年9月1日)は、日本の思想家、哲学者(歴史哲学)です。在学中の1922年には、マホメットの生涯を描いた長編戯曲『沙漠の光』を発表し、ベストセラーとなりました仲小路は、1930年に小島威彦らと科学アカデミアを創立し、佐々弘雄、三枝博音、飯島正、冨澤有爲男、唐木順三、渡辺一夫、服部之総らと共に活動しました。1940年には、小島とともにスメラ学塾を開校し、塾頭に末次信正海軍大将が就任しました。主な著作として、『太平洋侵略史』全6巻(1942年)や『世界戦争論』(2011年復刻)などがあります
とのこと
情報と謀略の記載を見るにあたり、スメラ学塾は戦前かなりの人気と思われる
特に印象的だったのは、ドイツとの中東ルートの連携、しかもインド独立を視野に入れた対英戦略を提示していたことです
イスラムと連帯し、石油の確保も行い、インドの独立運動と中東の反英感情を使って、英帝国の弱体化を図るためのネットワーク構築を日本が狙う
といったものです
現実は東に行ってしまい太平洋ルートでの玉砕になってしまうわけですが
北進南進かだけではなく東進西進の選択もあったのか思いました
その他にも、その時々の戦局であったり、未来の見通しであったり、すごい慧眼の持ち主と思いました
関連書籍を現在読んでる最中です
サイパン上陸以降からの終戦へと向けた中での陸軍、海軍の関係
本書を読んで痛感したのは、戦争末期の日本は、外敵との戦い以上に「内部の分裂」に苦しんでいたという点でしょうか
サイパンを取られたあとは、もうあかん、っていう認識が大多数にあったようにおもいます
しかし、特に陸軍と海軍の間にある深刻な齟齬は、国家の意思決定を著しく妨げ、情報の共有も和平交渉の一貫性も損なっています
戦争を終結に向かわせるには、国として明確な方針と戦略が必要ですが、それが日本には存在せず、悪戯に長引いてしまった
戦争末期、日本が「いかに終戦に持っていくか」を考える上で、陸軍と海軍の足並みの揃わなさ——その実態を『情報と謀略 下』は容赦なく描いていて、読んでいてしんどい部分もあるけれど、だからこそリアルと思いました
さらに情報機関もそれぞれバラバラで、海軍・陸軍・外務省・内務省がそれぞれ独自の情報ルートを持っていて、お互いに信用していない、だから重要な和平シグナルがうまく伝わらない
もはや情報の乱戦状態です
そういうのを知ると、「なぜ戦争が長引いたのか」「なぜもっと早く終わらせられなかったのか」っていう疑問にも答えが見えてくるし、「負けた」という事実の背後にある、被害を最小限にできたはずの失われたはずの無数のチャンスが浮かび上がってくる
国体を守るために無条件降伏を受け入れ難かったというのもあると思いますが
情報の大事さ、共有、連携の大事さが沁みます
終戦後の事件について
「厚木航空隊反乱」は、1945年8月15日の終戦詔書発表後にも戦争継続を主張して起きた、海軍航空隊の反乱未遂事件です
正式な「クーデター」とまでは至らなかったものの、終戦を拒否しようとした最後の抵抗のひとつとして、歴史的に非常に重要な事件です。
「8・15事件」は、1945年8月15日未明に起きた“宮城事件”(きゅうじょうじけん)の通称で、終戦を巡る日本の軍内部のクーデター未遂事件です。
終戦の詔書(玉音放送)を阻止しようとした事件で、戦争継続を望む一部の陸軍将校たちが、昭和天皇の詔書放送を止めようと皇居(宮城)を占拠しようとしたものです。
- 1945年8月14日夜、昭和天皇は御前会議でポツダム宣言の受諾を最終決定。
- 終戦の詔書(玉音放送)は録音され、翌15日正午に国民に向けて放送される予定だった。
- これに反発した一部の陸軍青年将校が、戦争継続を望んでクーデターを決行
教科書ではすんなり終戦しましたって感じがするのですが、クーデター紛いのことがもあったことを初めて知りました
まとめ
日本という国が内部の対立を抱えながら終戦を模索していたのかが伺えます
その過程で活躍した一部の情報将校や、仲小路彰氏のような異才の存在を通して、「情報と謀略」が単なる戦争の裏面史ではなく、国家の命運そのものを左右するものだったことを改めて実感します
教科書だけ見ても、こういった詳細はわからない
全く書いておらず、様々な本を読んで歴史を学び直す必要があると感じました
情報と言う観点から第二次世界大戦を見つめ直す良書と感じます
以上参考になれば幸いです



コメント